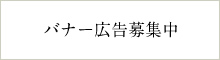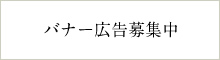百鬼夜行(ひゃっきゃこう)は、日本の伝統的な妖怪文化を象徴する幻想的な行列で、百体もの妖怪たちが夜の町を練り歩くとされる現象です。古くは災厄をもたらす存在とされましたが、現代ではその多彩で個性豊かな妖怪たちが、想像力を刺激する魅力的な存在として親しまれています。平安時代の陰陽師・賀茂忠行(かものただゆき)は、百鬼夜行に遭遇しながらも陰陽道の知識と術で無事に切り抜けたと伝えられ、知恵と精神力の象徴ともなっています。江戸時代には絵巻や浮世絵に描かれ、妖怪一体一体のユーモラスな姿や個性が人々の関心を集めました。百鬼夜行はただの怪異ではなく、人々の想像や風刺、自然や道具への畏敬の念を映す文化的モチーフです。今日ではアニメや漫画、イベントなどにも登場し、日本独自の豊かな想像世界を象徴する存在となっています。
百鬼夜行
Copyright(C) SHINJO CITY, Yamagata, Japan. All Rights Reserved.訪問者数:4825710